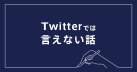業務効率化にご用心。だらしない人ほどうまくいく
いつもお久しぶりです。才流(サイル)の栗原です。
今日は効率化“しないこと”の効果に焦点をあてた書籍『だらしない人ほどうまくいく』を紹介します。ブラウザのタブも最小限しか開かず、デスクトップにファイルやアイコンはゼロで、メールのフォルダも常に未対応0件の、比較的効率化好きな私にはグサグサと刺さる本でした。
1.印象に残ったこと
本書の冒頭で、2つの対照的な本屋が紹介されている。
一方の店は、書籍が驚くほどきれいに並べられ、在庫はコンピュータで管理。もう一方の店は、書籍が乱雑に並べられ、店主はコンピュータも持っていない。
一方の店舗は赤字続きで、店を畳まざるを得なかったが、もう一方の店は利益を出しながら、いまも商売を続けている。
本書のタイトル『だらしない人ほどうまくいく』から推測できるように、利益を出しながら商売を続けているのは、書籍が乱雑に並べられ、店主がコンピュータを持っていなかった店だ。
商品をきれいに並べるための人件費、在庫管理のためのシステム導入費など、業務をきっちり、効率的にやるためのコストがかからず、利益を上げ続けることができたという。
この本を読んで思い出したのが、前職時代のエピソード。
私の100倍ほど仕事ができる先輩がいて、その先輩がお客様に提出する見積書は項目や備考がめちゃくちゃ詳細に書かれていた。仕事できるなー、さすがだなーと思っていたが、見積書の項目や備考の解釈についてお客様とよく揉めていたのだ。
一方、その先輩の100分の1しか仕事ができなかった私は、見積書の項目や備考をざっくり書いていて、必要最低限のことしか定義していなかったが、お客様と揉めた記憶がない。争うべき定義や解釈、項目がそもそも存在しないため、お客様と揉めようがなかったのだ。※細かい部分のすり合わせは都度、やりながら行っていたが
この経験から「過度な細かさはトラブルのもと」という自分に都合の良い学びを得ることになった。
もう一つのエピソードとして、私の観測範囲では「伸びてる会社のSFAはぐちゃぐちゃの法則」が存在する。商品やサービスが市場に受け入れられ、急成長している会社はSFAの項目を精緻に設計したり、営業パーソンに入力を徹底させる取り組みも間に合わないため、意外とSFAの設計や入っているデータがぐちゃぐちゃなことが多い。
SFAだけを見ると『全然ちゃんとしていない会社だな・・』と思うのだが、業績はぐんぐん伸び、市場や顧客に喜ばれている。
一方、商品やサービスが市場に受け入れられておらず、商談や受注・納品に忙しくない会社ほど、SFAが精緻に設計され、データがちゃんと入っていたりする。しかし、肝心の業績は伸びていない。
伸びている会社も、急成長した後、優れた営業企画やMarketing Opsが入社し、事後的にSFAがきれいに設計・運用され、あたかも「SFAをフル活用している業績の良い会社」になるわけであるが、業績向上のドライバーは、SFAの活用や効率的な営業活動“ではなく”、市場の大きさや成長率、商品・サービスの魅力、商談創出力、営業力などだ。
もちろん、例外的に
内部統制の重要性を知るシリアルアントレプレナー
資金調達をしていて、システムやオペレーションへの投資ができるスタートアップ
運良く、システムやオペレーション人材が採用できた企業
などは初期からSFAをきれいに設計・運用して、業績を伸ばすケースもあるし、後からデータ分析がしづらい弊害もあるので、理想論としては初期からSFAを活用するに越したことはない。
ただし、SFAの設計・運用などの「業務効率化」そのものが何かを生み出すわけではないことは忘れないようにしたい。
私たち人間は、試験前になると部屋や机の上を片付けたくなってしまう生き物だが、片付けをしても成績は伸びず、参考書を開いて勉強をすると成績は伸びる。
同様に、SFAの項目設計や精緻なデータ入力にこだわりたくなってしまうが、それ自体では業績は伸びず、顧客や商品・サービスの魅力に向き合ったり、そのために顧客とたくさん商談すると業績は上がる。
(部屋や机の上の片付けにあたる)業務効率化に夢中になっていないか?(参考書を開いて勉強することにあたる)実行に時間を使えているか?は自問し続ける価値のある問いだろう。
2. 抜粋とコメント
<きっちり>するにはコストがかかるという明白な事実を、世界はこれまで無視しつづけてきた。(中略)整理したり秩序だてたりすることは、そのために必要とされる時間や費用に見合っているのかということだ。
→効率化にも時間やコストがかかるし、効率的な状態を保つことにもまた時間やコストがかかる。そこも含めて、ROIが合っているのかを考えるべき。
逆に言うと、ある程度の<だらしなさ>を容認しさえすれば、相当額のコストを節約できるのだ。
→「効率化しない」と決めることは、逆説的だが、コスト削減にもなる。
実際、「いつも机が整頓されていると答えた人は、散らかっていると答えた人より、平均で三十六パーセント以上長い時間を探し物に費やしていた。
→効率化にあたって策定したルールブックを探したり、ルールを思い出したり、アップデートするのに時間を取られがち。
ほどほどにルーズな人間や組織やシステムのほうが、その逆の場合よりも、より能率的、弾力的、かつ創造的であり、より望ましい効果をあげることは珍しくない
→御意。
どんなにがんばっても、<だらしなさ>を完全に消し去ることはできない(中略)<だらしなさ系>の家庭や職場を嫌うのは、<だらしなさ>が実際に問題を引き起こすからではない。自分はもっと<きっちり>していなければならないと思いこみ、そうでないことに後ろめたさを感じているからなのだ。
→本書の中に、全米整理整頓協会的な団体のお偉いさんが「まだまだ自分のだらしなさに反省する日々だ」という記述があった。完璧なシステム、仕組み、人は存在しないのに、それを求めてしまう。
何かを完全な状態に保ちつづけるには、それなりの労力が必要となる。
→それなりどころか、それ以上の労力がいるので気をつけたい。
今後も才流を経営しながら考えたことや参考にした本の書評を更新していければと思っています。